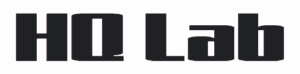「時間をかけて戦略を練ったのに、いつの間にか形骸化してしまった」「市場の変化が速すぎて、戦略が追いつかない」――多くの企業で聞かれる悩みです。素晴らしいアイデアも、具体的な行動に繋がらなければ成果は生まれません。この記事では、戦略を「机上の空論」で終わらせず、着実に成果へと結びつけるための新しいアプローチ、「リーン戦略策定プロセス」をご紹介します。従来の戦略策定の落とし穴を乗り越え、変化に強く、実行力のある戦略を組織に根付かせるヒントがここにあります。
なぜ、あなたの会社の戦略は「実行されない」のか?~よくある3つの落とし穴~
多くの企業が戦略を実行に移せない背景には、共通する課題が潜んでいます。まずは、自社が陥りがちな「落とし穴」を認識することから始めましょう。
落とし穴1:目指す姿が「フワッ」としている
戦略の第一歩は、明確な目標設定です。しかし、「業界No.1を目指す」「顧客満足度向上」といったスローガンだけでは、現場は何をすべきか分かりません。具体的で、測定可能で、かつ組織全体が「本気で達成したい」と思えるような、野心的でありながらもリアリティのある「勝利の姿」が描けているでしょうか?現状の延長線上ではない、本質的な変革を促すような目標設定が不可欠です。
落とし穴2:意思決定が「その場しのぎ」になっている
重要な戦略的意思決定が、担当役員の個性やその時々の状況によってバラバラなプロセスで行われていませんか?「A事業部ではこう決めたが、B事業部では全く違うやり方」では、組織全体として最適な判断はできません。場当たり的な意思決定は、遅れや質の低下を招き、大きな機会損失に繋がります。各決定がどのように行われたのか、なぜその選択肢が選ばれたのかが不明確なままでは、組織学習も進みません。
落とし穴3:「やりっぱなし」で誰も責任を持たない
どんなに優れた戦略も、実行されなければ意味がありません。そして、実行された結果を検証し、改善に繋げる仕組みがなければ、戦略は進化しません。「計画は立てたけれど、進捗を誰も追っていない」「結果が悪くても、原因分析や軌道修正が行われない」といった状態では、戦略は絵に描いた餅のままです。成果に対する責任の所在を明確にし、定期的に進捗と成果を評価する文化が求められます。
「勝てる戦略」を組織に根付かせる新常識~リーン戦略策定3ステップ~
これらの落とし穴を避け、戦略を確実に成果に結びつけるために提案したいのが、「リーン戦略策定」という考え方です。これは、製造業の「リーン生産方式」の思想を戦略策定に応用し、無駄を徹底的に排除し、価値創造に集中するアプローチです。具体的には、以下の3つのステップで進めます。
ステップ1:【現状打破の羅針盤】野心的な「勝利の姿」と本質的な「戦略課題」を明確にする
まず、数年後を見据えた「野心的な業績目標(Performance Ambition)」を定義します。これは単なる予算目標ではなく、組織を奮い立たせ、ブレークスルーを生み出すための挑戦的な目標です。次に、現在の戦略を継続した場合の「中期事業見通し(Multiyear Outlook – MYO)」を冷静に評価します。この2つの間にあるギャップこそが、戦略で埋めるべき課題です。
そして、このギャップを埋めるために取り組むべき最も重要な戦略的・組織的課題を「戦略課題リスト(Strategic Backlog)」として文書化し、優先順位をつけます。優先順位付けは、「解決した場合のインパクトの大きさ」と「緊急性・他の課題への影響度」を基準に行います。
ポイント:課題は具体的に記述し、「どの市場でシェアをどう拡大するか?」といったように、何を解決すべきかを明確にすることが重要です。「会社Xを買収して市場Yに参入すべきか?」のような、解決策を限定する問いの立て方は避けましょう。
ステップ2:【最善手を見抜く】標準化された「意思決定サイクル」を回す
特定された戦略課題に対して、標準化された意思決定プロセスを適用します。これにより、意思決定の質とスピードが向上します。このプロセスは、主に2つの会議体で構成されます。
- 1. 事実と代替案の創出セッション:課題を深く理解し、その根本原因を特定し、対処するための多様な選択肢を洗い出します。ここでは結論を急がず、質の高い選択肢を幅広く検討することが目的です。市場データだけでなく、自社の強みや弱み、顧客インサイトなど、多角的な情報収集と分析が鍵となります。
- 2. 選択とコミットメントセッション:提示された代替案を、事前に合意された評価基準(例:将来のキャッシュフローへの貢献度など)に基づいて評価し、最適なものを選択します。そして、選択した戦略を実行するために必要なリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)をコミットし、具体的な実行計画とマイルストーンを定めます。
ポイント:「何を行うか」だけでなく「何を行わないか」を明確にすることも重要です。意思決定のプロセスと結果は「意思決定ログ」として記録し、組織内で共有することで、曖昧さを排除し、実行への迷いをなくします。
さらに、戦略課題に取り組むタイミングと責任者を明確にした「意思決定カレンダー」を作成し、経営会議などの場で定期的に進捗を確認・議論するリズムを作ります。これにより、重要な課題が先送りされることなく、着実に処理されていきます。
ステップ3:【進化し続ける戦略】「実績評価」と「機敏な軌道修正」を習慣化する
戦略は一度作ったら終わりではありません。市場環境や競争状況は常に変化します。そのため、定期的な「業績評価レビュー」を通じて、戦略の実行状況と成果を厳しくチェックし、必要に応じて軌道修正を行うことが不可欠です。
このレビューでは、単に予算と実績の差異を確認するだけでなく、「なぜ差異が発生したのか?」「前提条件に変化はなかったか?」「より良い戦略的選択肢は存在しないか?」といった本質的な問いを立てることが重要です。もし、市場環境の大きな変化などにより、前提が覆された場合は、該当する課題を再び「戦略課題リスト」に戻し、再検討する柔軟性も求められます。
ポイント:業績が計画を上回った場合も、「なぜ上手くいったのか?」を分析し、成功要因を特定して組織全体で共有することで、さらなる成長に繋げることができます。
事例から学ぶ「リーン戦略」の威力
このリーン戦略策定アプローチは、既に多くの先進企業で導入され、目覚ましい成果を上げています。
- あるグローバルIT企業(例:Googleに着想を得て):「既存の10倍優れたものを目指す」という野心的な目標設定文化を醸成。これにより、ストレージ容量が他社の100倍もあるメールサービスや、自動運転技術といった革新的なサービスを次々と生み出し、市場をリードし続けています。
- ある大手テクノロジー企業(例:Dellに着想を得て):市場投入モデルの抜本的な再設計という複雑な課題に対し、標準化された意思決定プロセスを適用。営業体制の最適化や製品ラインナップの見直しといった複数の重要判断を迅速かつ的確に行い、主要製品カテゴリでの市場シェア拡大に成功しました。この企業では、事業売却や社名変更といった重大な経営判断にも同様のプロセスが活用されています。
- ある先進的なバイオ製薬企業(例:Amgenに着想を得て):トップ経営層が参加する月次の業績評価会議で、「パフォーマンス・ダイアログ(業績対話)」と呼ばれる仕組みを導入。戦略課題リストに対するコミットメントの進捗を厳しくチェックし、課題があればその場で原因分析と対策を議論します。また、主要な経営指標をリアルタイムで可視化するプラットフォームを活用し、データに基づいた迅速な意思決定と軌道修正を実現。結果として、ブロックバスター(大型医薬品)の数を大幅に増やし、企業価値を飛躍的に向上させました。
結論:戦略策定を「組織の強み」に変え、持続的成長を実現する
戦略的意思決定を、一部の天才に依存する「アート」から、組織全体で実践可能な「標準化されたプロセス」へと転換すること。これこそが、変化の激しい時代において企業が競争優位を確立し、持続的な成長を遂げるための鍵となります。
リーン戦略策定プロセスは、優先順位を明確にし、事実に基づいた質の高い選択肢を生み出し、明確な意思決定を下し、具体的な実行計画を策定し、その進捗を厳しく管理することを組織に根付かせます。このアプローチを全社的に展開することで、意思決定の質とスピードが向上し、組織の実行力は飛躍的に高まるでしょう。
まずは、自社の戦略策定プロセスを見直すことから始めてみませんか?小さな一歩が、企業の未来を大きく変える力となるはずです。