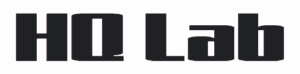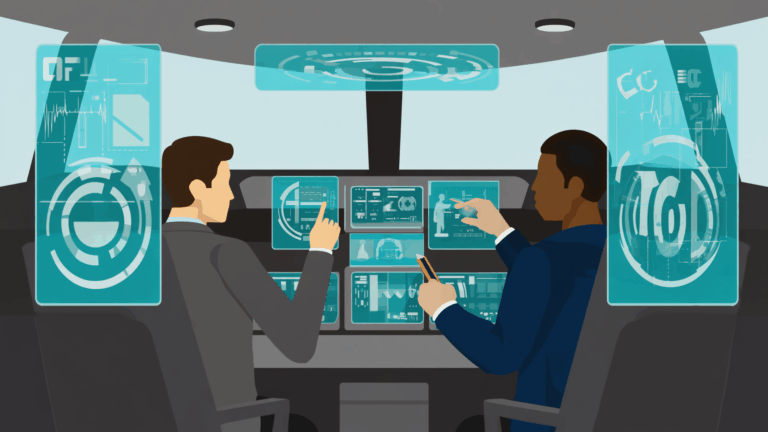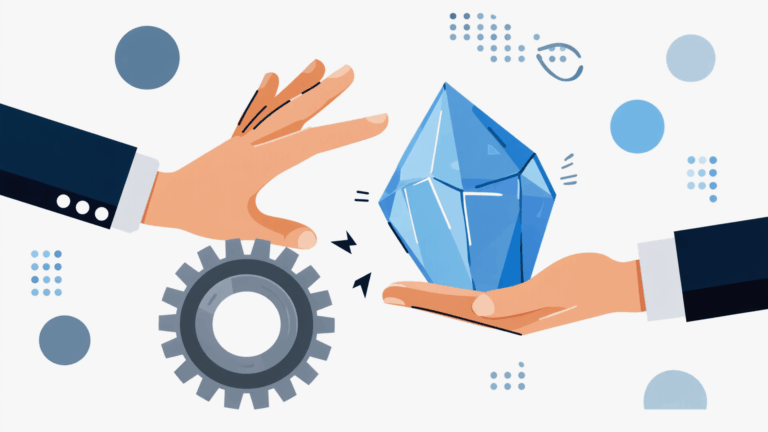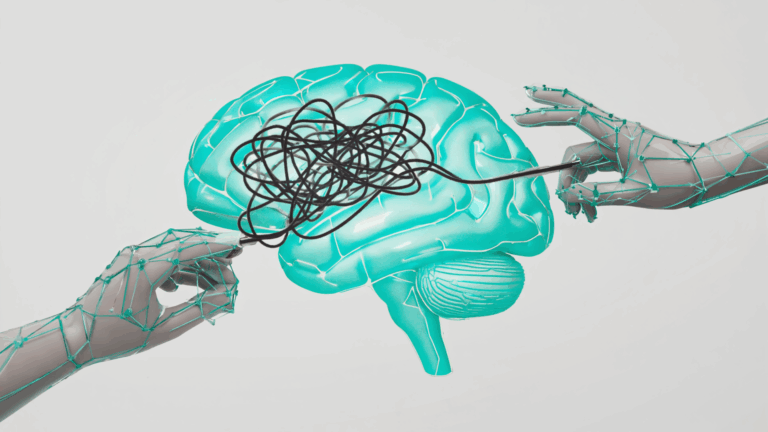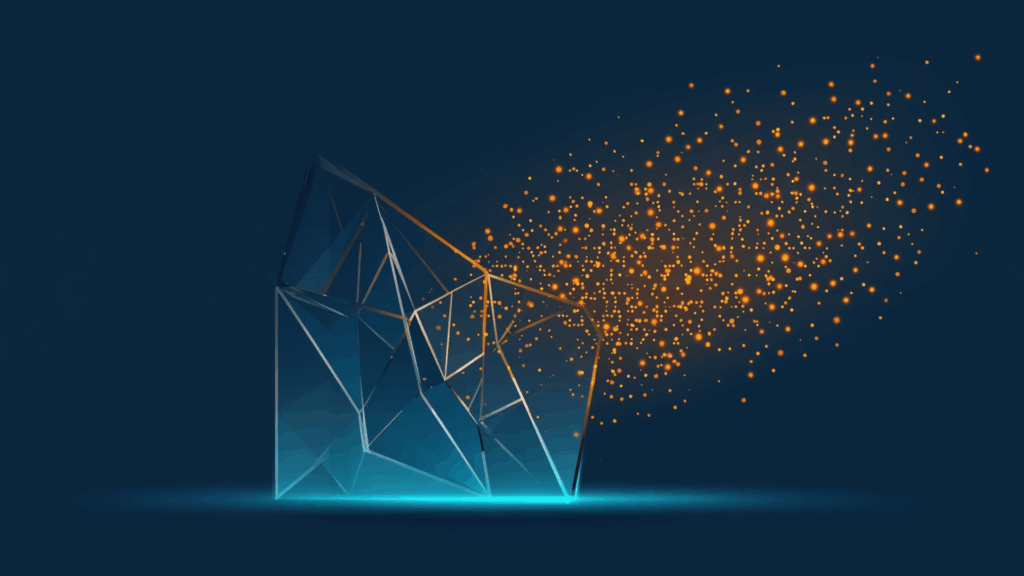
現代の経営環境は、かつてないほどの速度と複雑性をもって変化しています。このような時代において、企業が持続的な成長を遂げるためには、既存事業の深化と新規事業の探索を同時に追求する「両利きの経営(Ambidextrous Management)」の重要性がますます高まっています。しかし、その概念を理解していても、実際に自社でどのように実践すれば良いのか、多くの経営者や事業責任者が頭を悩ませているのではないでしょうか。特に、歴史ある大企業や中堅企業にとっては、既存事業の巨大な慣性と成功体験が、新たな挑戦への足枷となることも少なくありません。
この記事では、「両利きの経営」を実践する上で企業が直面する具体的な「壁」と、それを乗り越えるための「突破口」について、国内外の事例、特に日本企業が陥りがちな課題とその克服策に焦点を当てながら深掘りします。理論の解説に留まらず、具体的な組織設計の考え方、人材配置の妙、成功と失敗から学ぶべき教訓、そしてHQLab独自のフレームワークや経営者の生々しい経験談を交えながら、読者の皆様が自社の状況を診断し、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントを提供します。
なぜ今、多くの企業が「両利きの経営」に注目するのか

市場の成熟化、グローバル競争の激化、破壊的イノベーションの出現など、企業を取り巻く環境は常に変化しています。過去の成功モデルが通用しなくなり、既存事業だけに依存していては、いずれジリ貧に陥るリスクがあります。一方で、不確実性の高い新規事業への投資は、短期的な収益圧迫や失敗のリスクを伴います。「両利きの経営」は、このジレンマに対する一つの解として注目されています。
既存事業で培った強み(顧客基盤、技術力、ブランド力など)を活かしながら、新たな成長エンジンとなる新規事業を育成すること。それは、短期的な収益確保と長期的な成長機会の獲得を両立させる道筋であり、企業の持続可能性を高める上で不可欠な戦略と言えるでしょう。しかし、その実践は容易ではありません。なぜなら、既存事業の「深化(Exploitation)」と新規事業の「探索(Exploration)」は、求められる組織文化、プロセス、評価基準、人材のスキルセットなどが大きく異なるからです。
「両利きの経営」実践を阻む日本企業特有の壁
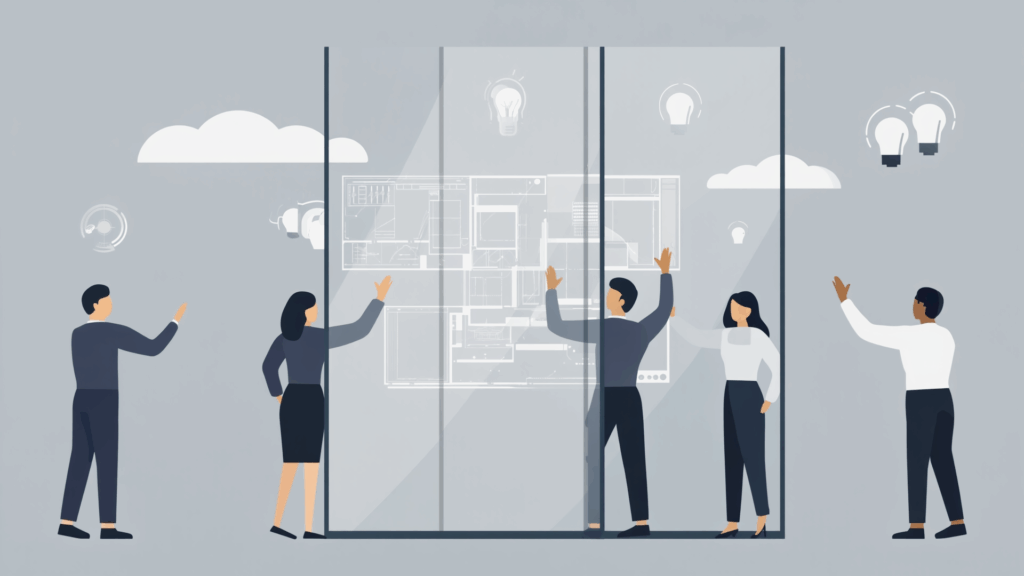
「両利きの経営」の難しさは世界共通ですが、特に日本企業においては、独自の組織文化や構造的な課題が実践をより困難にしている側面があります。具体的にどのような壁が存在するのでしょうか。
既存事業の成功体験と「減点主義」の文化
長年にわたり成功を収めてきた事業部門は、その成功体験への固執や、失敗を恐れる「減点主義」の文化が根付きやすい傾向にあります。新しいアイデアや挑戦に対して、「前例がない」「リスクが高い」といった理由で否定的な意見が出やすく、イノベーションの芽を摘んでしまうことがあります。また、既存事業の効率性や生産性を追求するプロセスが、新規事業の探索活動とは相容れないことも少なくありません。
短期的な成果を重視する評価制度とリソース配分の偏り
多くの日本企業では、依然として短期的な財務成果を重視する評価制度が主流です。成果が出るまでに時間を要し、不確実性の高い新規事業は評価されにくく、担当者のモチベーション維持も困難になります。結果として、有望な新規事業のアイデアがあったとしても、リソース(人材・資金・時間)が既存事業に優先的に配分され、新規事業は十分な支援を受けられないまま立ち消えになってしまうケースが見られます。
縦割り組織と部門間のサイロ化
伝統的な日本企業に多く見られる縦割り組織は、部門間の連携を阻害し、知識や情報の共有を困難にします。「両利きの経営」では、既存事業の知見を新規事業に活かしたり、逆に新規事業から得た洞察を既存事業の革新に繋げたりといったシナジー効果が期待されますが、部門間の壁が高いと、こうした連携は生まれにくくなります。
意思決定プロセスの遅延とコンセンサス重視の弊害
変化の速い市場環境に対応するためには、迅速な意思決定が不可欠です。しかし、日本企業特有のボトムアップ型の意思決定プロセスや、関係者全員のコンセンサスを重視する文化は、時に意思決定の遅延を招き、新規事業の機会を逸してしまう原因となります。「両利きの経営」を推進するためには、トップの強いリーダーシップと、ある程度の試行錯誤を許容する柔軟な意思決定メカニズムが求められます。
壁を突破するための鍵:事例に学ぶ組織戦略と実践フレームワーク
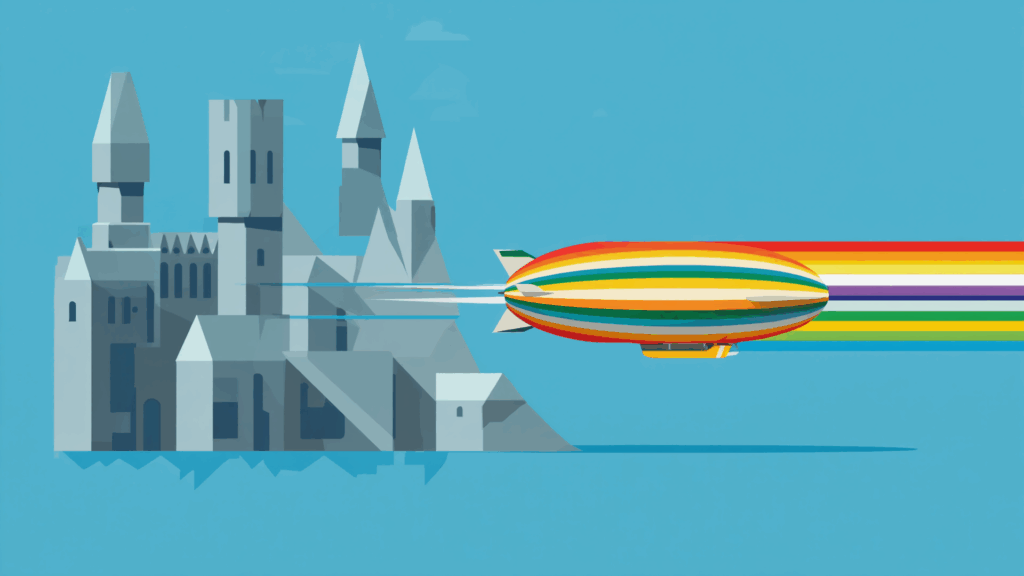
これらの壁を乗り越え、「両利きの経営」を成功に導くためには、どのような組織戦略やアプローチが有効なのでしょうか。国内外の先進企業の事例や、HQLabが提唱する実践フレームワークから、そのヒントを探ります。
【事例分析】成功企業と失敗企業、その差はどこにあるのか
国内外には、「両利きの経営」に挑戦し、目覚ましい成果を上げた企業もあれば、残念ながら道半ばで頓挫してしまった企業も存在します。
例えば、あるグローバル企業は、既存事業部門とは完全に独立した新規事業開発部門を設立し、異なる評価基準やプロセスを導入することでイノベーションを加速させました。一方で、別の企業では、既存事業の論理で新規事業を評価し続けた結果、有望なプロジェクトが次々と中止に追い込まれました。日本企業の中にも、トップの強いコミットメントのもと、社内ベンチャー制度や出島組織(既存組織から物理的・組織的に分離したチーム)を活用し、既存事業とのカニバリゼーションを恐れずに新規市場を開拓した事例があります。これらの事例から見えてくるのは、トップの明確なビジョン、探索活動に適した組織構造の設計、そして失敗を許容し挑戦を奨励する文化の重要性です。
実践フレームワーク
数多くの企業変革を支援してきた経験豊富なコンサルタントの知見に基づき、「両利きの経営」を実践するために活用できる具体的なフレームワークを紹介します。
このフレームワークは、以下のステップで構成されます。
- ビジョン共有と危機意識の醸成:なぜ「両利きの経営」が必要なのか、経営トップが明確なビジョンを示し、組織全体で危機意識を共有することから始めます。
- 探索領域の特定と戦略策定:自社の強みや将来の市場機会を踏まえ、どの領域で「探索」を行うのかを特定し、具体的な戦略を策定します。
- 最適な組織構造の設計:「深化」と「探索」の活動を両立させるための組織構造を設計します。これには、構造的分離(独立部門の設置)、時間的分離(既存部門内で探索活動の時間を確保)、あるいは文脈に応じた使い分け(個々の従業員が状況に応じて深化と探索を使い分ける)など、様々なアプローチがあります。
- 人材の育成と配置:「深化」と「探索」それぞれに適した人材像を定義し、育成・配置を行います。特に「探索」を担う人材には、不確実性への耐性、学習意欲、起業家精神などが求められます。
- 評価・報酬制度の見直し:「探索」活動を適切に評価し、挑戦を促すための評価・報酬制度を設計します。短期的な成果だけでなく、学習や試行錯誤のプロセスも評価対象に含めることが重要です。
- イノベーション文化の醸成:失敗を許容し、挑戦を奨励する企業文化を醸成します。心理的安全性の確保や、部門を超えたコミュニケーションの活性化が鍵となります。
このフレームワークは、画一的なものではなく、各企業の状況や特性に応じてカスタマイズしながら適用することが可能です。
経営者の生の声から学ぶ「両利きの経営」のリアル
弊社が実施した経営者インタビューからは、「両利きの経営」を推進する上でのリアルな葛藤や、それを乗り越えるための知恵が垣間見えます。ある経営者は、「既存事業を守る責任と、未来への投資のバランスに常に悩まされた。しかし、社員の目の輝きが変わっていくのを見て、この道しかないと確信した」と語ります。また、別の経営者は、「最初の数年間は全く成果が出ず、社内からの風当たりも強かった。それでも信じて投資を続けた結果、ようやく花開いた」とその道のりの険しさを吐露しています。これらの生々しい経験談は、理論だけでは得られない貴重な学びを与えてくれます。
「両利きの経営」を軌道に乗せる具体的な組織戦略
フレームワークを理解した上で、具体的にどのような組織戦略を講じれば、「両利きの経営」を軌道に乗せることができるのでしょうか。
探索と深化、双方を活かす人材配置と育成
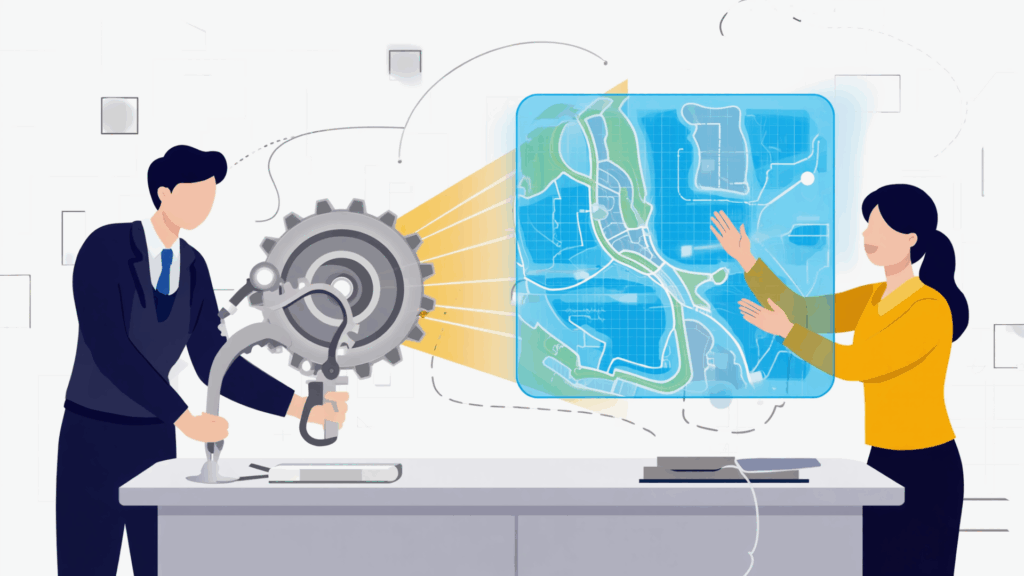
「両利きの経営」を成功させるためには、既存事業の効率性を追求する「深化型人材」と、新しい可能性を追求する「探索型人材」の双方が必要です。重要なのは、これらの人材を適材適所に配置し、それぞれの強みを最大限に活かすことです。また、将来的には両方の能力を兼ね備えた「両利き人材」を育成することも視野に入れるべきでしょう。そのためには、異動や兼務、社内外の研修プログラムなどを通じて、多様な経験を積む機会を提供することが有効です。特に「探索型人材」に対しては、裁量権を与え、失敗から学ぶ機会を保障することが成長を促します。
イノベーションを測定するKPIと評価制度の再構築
既存事業のKPI(重要業績評価指標)は、売上や利益率、市場シェアといった財務指標が中心となるのが一般的です。しかし、これらのKPIをそのまま新規事業に適用すると、早期に成果が出にくい探索活動は正当に評価されず、担当者の士気低下やプロジェクトの中断につながりかねません。新規事業のフェーズに応じて、学習の進捗度、顧客からのフィードバック獲得数、試作品の開発スピード、市場仮説の検証回数といった、非財務的なKPIを設定することが重要です。評価制度も、短期的な成果だけでなく、挑戦したこと自体や、失敗から得た学びを評価する仕組みを取り入れる必要があります。
部門横断的な連携と知識共有を促す組織文化
既存事業の知見やリソースを新規事業に活用したり、新規事業で得たアイデアを既存事業の改善に繋げたりするためには、部門を超えたコミュニケーションと知識共有が不可欠です。社内SNSの活用、部門横断プロジェクトの推進、定期的なアイデアソンやワークショップの開催などを通じて、組織の風通しを良くし、サイロ化を防ぐ努力が求められます。また、経営トップ自らが部門間の連携の重要性を発信し、協力的な行動を奨励することも有効です。
自社の現在地を知る:「両利きの経営」実践度診断チェックリスト
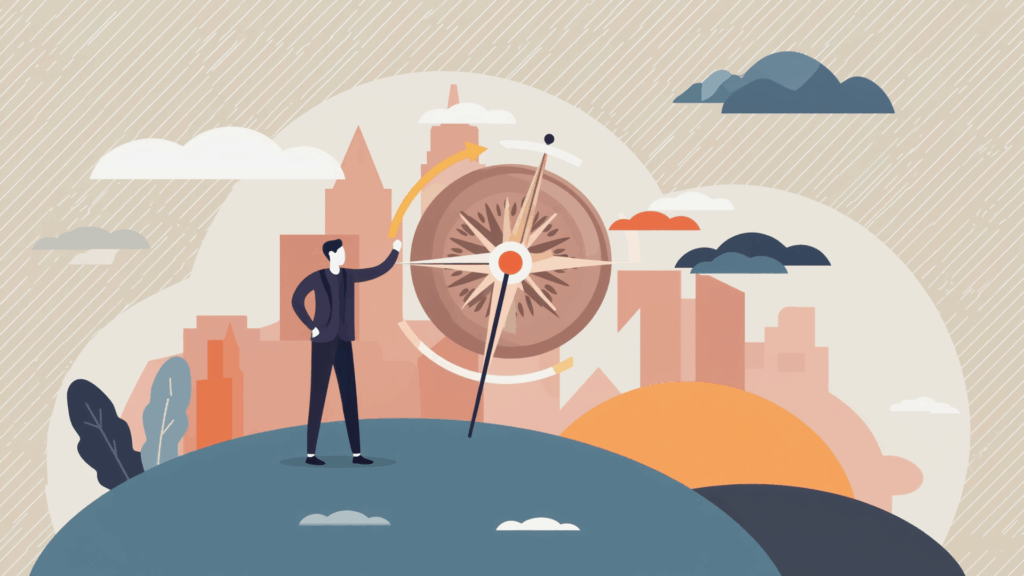
「両利きの経営」を推進する上で、まずは自社がどの程度、その準備ができているのか、あるいはどのような課題を抱えているのかを客観的に把握することが重要です。以下のチェックリストを活用し、自社の「両利きの経営」実践度を診断してみましょう。
- ビジョンと戦略:
- 経営トップは、「両利きの経営」の重要性を明確に認識し、社内に発信しているか?
- 既存事業の維持・強化と、新規事業の創出・育成の双方にコミットしているか?
- 新規事業の探索領域や目標が具体的に定義されているか?
- 組織とプロセス:
- 新規事業開発を専門に行う部門やチームが存在し、一定の独立性が保たれているか?
- 新規事業のアイデアを迅速に検証し、意思決定できるプロセスがあるか?
- 既存事業部門と新規事業部門の間で、必要な情報や知識が共有される仕組みがあるか?
- 人材と評価:
- 新規事業に挑戦する人材を積極的に登用・育成しているか?
- 新規事業の特性に合わせた評価基準やインセンティブ制度が導入されているか?
- 失敗から学び、再挑戦することを奨励する風土があるか?
- 文化とリーダーシップ:
- 組織全体として、変化を恐れず新しいことに挑戦する意欲があるか?
- 部門間の壁が低く、オープンなコミュニケーションが取れているか?
- ミドルマネジメント層は、「両利きの経営」の推進に協力的か、あるいは抵抗勢力となっていないか?
これらの質問に対して、「はい」と答えられる項目が少ないほど、「両利きの経営」を実践する上での課題が多いと考えられます。診断結果を踏まえ、自社が特に注力すべき改善ポイントを特定し、具体的なアクションプランに繋げていくことが重要です。
明日から始める「両利きの経営」への最初の一歩
「両利きの経営」の実践は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。しかし、変化を恐れず、粘り強く取り組むことで、企業は持続的な成長と競争優位性を確立することができます。この記事で紹介した視点やフレームワークが、皆様の企業における「両利きの経営」推進の一助となれば幸いです。
まずは、自社の現状を客観的に把握することから始めてみましょう。そして、経営陣を含めた関係者間で、「なぜ今、両利きの経営が必要なのか」「どのような未来を目指すのか」について徹底的に議論することが、変革への第一歩となります。小さな成功体験を積み重ねながら、組織全体で学習し、進化していくこと。それこそが、「両利きの経営」を成功に導くための最も確実な道と言えるでしょう。